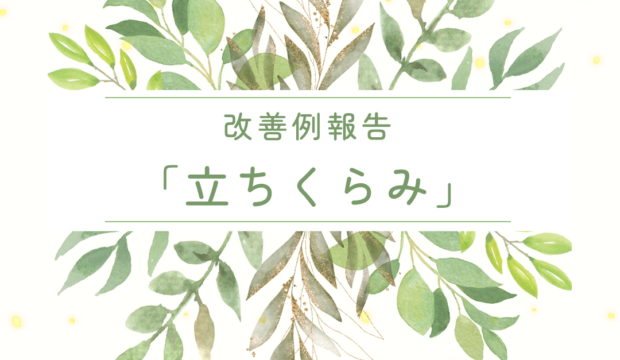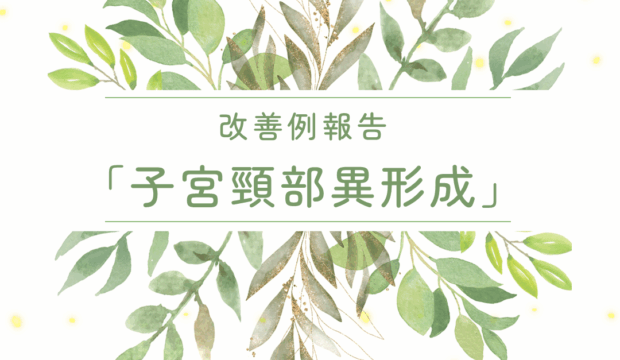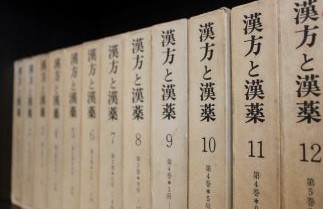こうも暑さが続くと、「体が重い」「やる気が出ない」「食欲がわかない」といった“だるさ”を感じる方が増えます。冷房や冷たい飲み物でリフレッシュしても、根本的な改善にはつながらず、毎日の生活に支障をきたすこともあります。東洋医学では、この“夏のだるさ”をどのように捉え、整えていくのでしょうか。
夏のだるさの原因とは?
東洋医学では、体調の不調を「外からの影響(外邪)」と「内側のバランスの乱れ」で説明します。夏のだるさは、主に以下の三つが大きな要因です。
- 暑さ(暑邪)の影響
夏の強い暑さは、体力や気を消耗しやすく、疲労感やだるさの原因になります。特に汗を大量にかくと、体の水分とともに気も失われ、倦怠感が増してしまいます。 - 湿気(湿邪)の影響
梅雨から夏にかけては湿度が高く、体内にも“湿”が溜まりやすくなります。湿は重く、停滞する性質を持つため、体が重だるく感じたり、食欲が落ちたりする原因になります。 - 冷えとのアンバランス
冷房や冷たい飲み物は、一時的には快適ですが、内臓を冷やしすぎてしまうことも。胃腸(脾胃)が冷えると、栄養をエネルギーに変える力(気)が弱まり、余計にだるさを感じやすくなります。
東洋医学的な対策
では、この“夏のだるさ”を和らげるために、どんな工夫ができるでしょうか。ポイントは「気の消耗を防ぐ」「湿をためない」「内臓を冷やしすぎない」の3点です。
1. 栄養をしっかり補う
夏はそうめんや冷たい麺類など、あっさりしたものに偏りがちですが、これでは気を補えません。鶏肉や豆類、旬の野菜をバランスよく取り入れることで、体力の土台が整います。
2. 湿を追い出す食材をとる
はとむぎ、とうもろこし、冬瓜、きゅうりなどは体の余分な水分を排出する働きがあります。スープや煮物に加えると、内臓を冷やしすぎずに摂取できます。
3. 冷え対策を忘れない
冷房の効いた室内では羽織りものを用意し、冷たい飲み物はほどほどに。常温の水や温かいお茶を取り入れると、胃腸の負担が軽減されます。
4. 睡眠と休養
気を補うには、質のよい睡眠が欠かせません。寝苦しい夜には、入浴で一度体温を上げてから眠ると、深い睡眠につながります。
おわりに
夏のだるさは、単なる疲れではなく、体と環境とのアンバランスから生じています。東洋医学の知恵に学びながら、食事や生活習慣を工夫することで、だるさを和らげ、残暑を元気に乗り切ることができます。まだまだ暑さが続くこれからの時期に改めて気をつけていきましょう!
伝統漢方火の鳥ではお客様一人ひとりの体質や症状に合った漢方薬をオーダーメイドで調合しております。
店舗は東京都多摩地域、八王子・立川・昭島・日野にございます。
ご予約はこちらからどうぞ。ご予約なしでもご来店OKです。
メールやお電話でのリモート相談および全国配送も行っております。
(※海外への発送も再開しております。気兼ねなくご相談ください。)