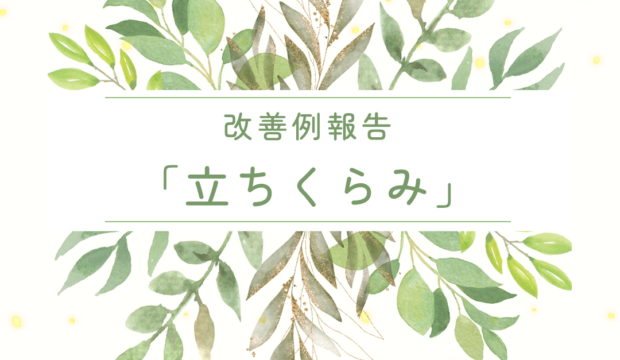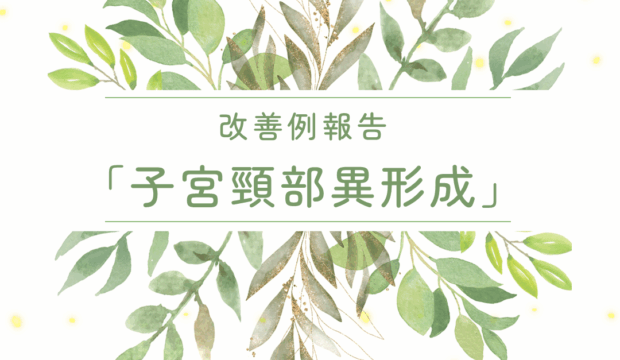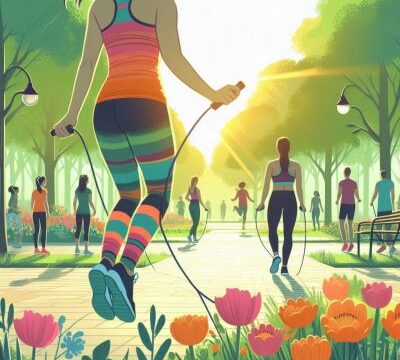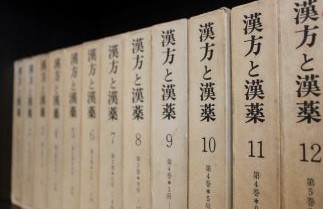秋から冬へ向かうこの時期、肌のカサつきや喉の違和感、便秘などを感じていませんか?
空気の乾燥は、知らず知らずのうちに体の“潤い”を奪い、さまざまな不調の原因になります。
漢方では、この「潤い」をどう保つかが、冬を元気に過ごすための大切な鍵とされています。
乾燥の季節は「潤い」がテーマ
気温が下がると同時に湿度も下がり、空気が乾いてくる秋。暖房の使用が増える冬には、さらに乾燥が進みます。
乾きは肌や喉、鼻といった粘膜だけでなく、体内の水分バランスにも影響します。結果として、咳・喉の痛み・便秘・イライラなどが起こりやすくなります。
東洋医学では、この季節に起こる“乾き”の症状を「燥邪(そうじゃ)」と呼び、体の潤いを失わせる外的な影響として捉えます。
つまり、この季節の養生は、「潤いを守ること=燥邪を防ぐこと」なのです。
「肺」を潤すことが全身を守る
漢方の考え方では、「肺」は呼吸だけでなく、皮膚や粘膜を潤す働きを持つ臓腑とされています。肺が乾くと、咳や鼻の不調だけでなく、肌荒れや便秘にもつながります。肺を守るには、「潤いを補う食材」を意識して取り入れることが効果的です。
たとえば、れんこん・大根・白きくらげ・ゆり根・梨・はちみつなどの“白い食材”は、肺を潤す代表格。
これらは体を内側からしっとりと整え、乾きによる不調を和らげます。
食卓でできる“潤い補給”
忙しい日々でも簡単に取り入れられる潤いレシピを紹介します。
〈れんこんと梨の潤いスープ〉
れんこん(薄切り)1節、梨1/2個、鶏ささみ1本、生姜少々、水500ml。
鍋に材料をすべて入れ、弱火で20分ほど煮込み、塩で味を整えます。
れんこんのとろみと梨の自然な甘みが、喉をやさしく潤してくれます。風邪のひき始めや乾いた咳にもおすすめです。
また、白きくらげを使ったデザートも効果的。白きくらげを水でもどし、なつめやクコの実と一緒に甘く煮ると、美肌と潤いを同時にサポートする一品になります。
日常のちょっとした潤い習慣
食だけでなく、生活の中でも乾きを防ぐ工夫ができます。
・加湿器や濡れタオルで部屋の湿度を保つ
・1時間に一度は深呼吸し、鼻から吸って口からゆっくり吐く
・ぬるめのお風呂でじんわり温まり、保湿を忘れない
特に呼吸は、肺を潤す基本。浅い呼吸を続けると、乾燥による咳やだるさが出やすくなります。意識して深く息を吐くことで、肺がほぐれ、全身の巡りも良くなります。
潤いをたたえて、やさしく冬を迎える
「潤い」は見た目の美しさだけでなく、生命力そのもの。
冬を健やかに過ごすためには、外からの保湿よりも、体の内側に“しっとりとした余裕”を育てることが大切です。
れんこんのスープを飲む時間、深呼吸をするひととき――そんな小さな積み重ねが、心と体にやさしい潤いをもたらします。
乾燥の季節こそ、自分の体をいたわる絶好のチャンス。
潤いをたたえて、冬をしなやかに迎えましょう。
伝統漢方火の鳥ではお客様一人ひとりの体質や症状に合った漢方薬をオーダーメイドで調合しております。
店舗は東京都多摩地域、八王子・立川・昭島・日野にございます。
ご予約はこちらからどうぞ。ご予約なしでもご来店OKです。
メールやお電話でのリモート相談および全国配送も行っております。
(※海外への発送も再開しております。気兼ねなくご相談ください。)