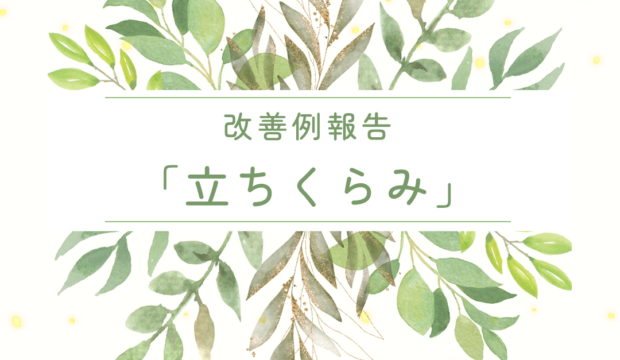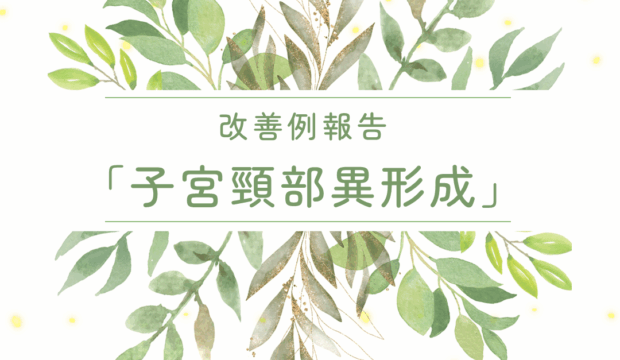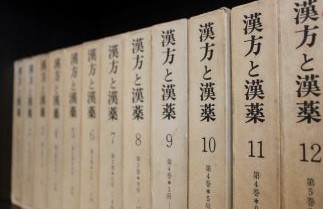寒さが深まる季節、気づくと足先が冷たくなっていませんか?
「冷え」は単なる不快感ではなく、体全体の巡りを乱す大きな要因です。特に秋から冬にかけては、下半身の冷えがじわじわと身体の中心に影響していきます。
冷えは「下」から忍び寄る
冷たい空気は自然と下にたまり、足先から体を冷やします。足の冷えを放置すると、血流が滞り、肩こり・腰痛・倦怠感・月経不調など、さまざまな不調へとつながります。冷えを感じやすい人ほど、まずは「足もと」から温めることが大切です。
「腎」を守ることが冬の養生の基本
漢方では、冬は「腎」の季節とされます。「腎」は生命エネルギーの源であり、成長や生殖、老化にも関わる重要な臓腑。寒さに弱く、冷えが続くと「腎」の働きが衰え、体力や気力の低下につながります。
冬の養生は、「腎」を冷やさないこと、つまり“体の芯を守る”ことから始まります。
日常でできる3つの温め習慣
① 足湯を習慣に
夜、洗面器にお湯を張り、足首まで10〜15分ほど温めます。お湯に少量の塩や生姜のスライスを加えると、より発汗が促されます。
② 腰と足首を冷やさない
腹巻きやレッグウォーマーを活用し、下腹部と足首を守りましょう。冷えが強い人は、寝る前にカイロを腰に当てるのもおすすめです。
③ しょうが湿布で芯から温める
薄切りのしょうがを熱湯に浸し、布で絞って腰や下腹部に当てます。芯からじんわり温まり、冷えだけでなく疲労回復にも効果的です。
体を温める食の知恵
食材にも“温める性質”があります。しょうが、にんにく、ねぎ、シナモン、黒ごま、羊肉などは代表的な温性食品。反対に、生野菜や冷たい飲み物は体を冷やします。
特に冬は、煮る・蒸す・焼くといった「温める調理法」を意識しましょう。朝は温かい味噌汁、夜は根菜たっぷりの鍋料理など、日々の食卓がそのまま養生になります。
温めは“無理なく続ける”がいちばん
冷え対策は、短期間で効果を求めず、毎日の積み重ねが大切です。忙しい日々の中でも、「足を温めて寝る」「冷たい飲み物を避ける」など、できる範囲で続けることが、冬を元気に過ごす最大の秘訣です。
足もとを温めることは、体を思いやる最初の一歩。やさしい温かさが、心までほっと和らげてくれます。
伝統漢方火の鳥ではお客様一人ひとりの体質や症状に合った漢方薬をオーダーメイドで調合しております。
店舗は東京都多摩地域、八王子・立川・昭島・日野にございます。
ご予約はこちらからどうぞ。ご予約なしでもご来店OKです。
メールやお電話でのリモート相談および全国配送も行っております。
(※海外への発送も再開しております。気兼ねなくご相談ください。)